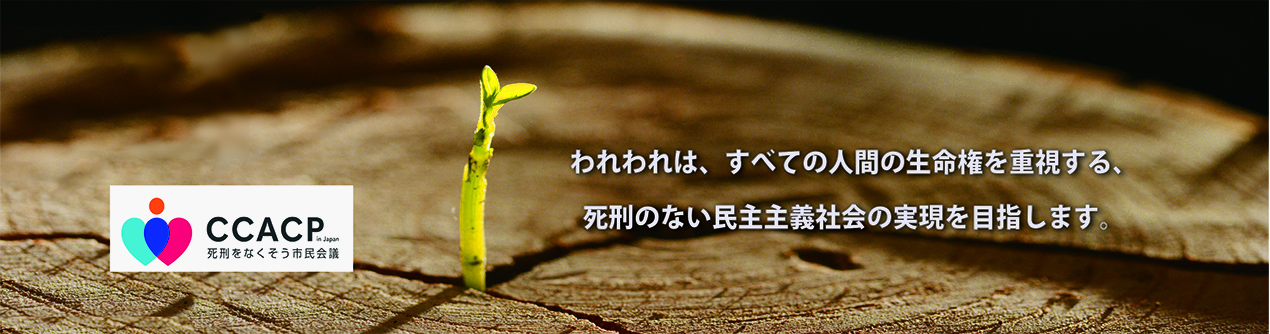― 多様な声と対話から見えた、制度の限界と私たちの課題 ―
片山徒有(被害者と司法を考える会代表)
(・・・トップページからの続きです)
中でも、印象深かったのは「死刑は遺族に正義をもたらすのか?」という問いに向き合う議論です。実際に「執行されて気持ちが整理された」と語る遺族の声が紹介される一方、支援が不十分なまま長年苦しみ続けている遺族の実情も共有されました。そこには「感情」と「制度」が乖離する現実が横たわっています。
日本の被害者支援は警察主導で一定の枠組みが整っていますが、冤罪や死刑を含む長期化する事件では支援が途中で途切れるケースも少なくありません。例えば、起訴後に始まる公的支援弁護士制度も、刑事裁判が終われば打ち切られ、法テラスの支援にも年数制限が課されている現状があります。
さらに、犯罪被害者等給付金制度においては、被害者の経済状況によって支給額が大きく変動し、専業主婦や学生などの「収入のない」立場の人々が、極端に少ない給付しか受けられないという実態もあります。こうした制度の不備が、「せめて死刑にしてほしい」という重罰志向に結びついてしまう構造があるのではないかと、私は感じています。
同時に、私は加害者の更生にも関心を寄せてきました。2000年代以降、矯正教育は大きく進化し、教育プログラムも多様化しました。今年6月からは拘禁刑も導入され、処遇段階は24に細分化され、個別に応じたきめ細かな対応が可能になっています。法務省が掲げた「矯正を社会の最後の砦とする」というミッション・ビジョン・バリューのもと、職員の意識改革も始まりました。
しかし、この矯正改革の波が死刑囚には一切届いていないという現実があります。死刑判決を受けた者は、教育プログラムの対象から外され、篤志面接委員との接触も禁じられています。死刑囚には更生の機会すら与えられない。これは「命を絶つ」ことだけを目的とする制度の非人道性を象徴しているように思えてなりません。
死刑制度をどう位置づけるかは、単に犯罪への応報という枠にとどまりません。それは私たちの社会が、被害者にも加害者にも、そして制度全体にどのように向き合おうとしているのかを示す「社会の鏡」であると、私は懇話会の議論を通じて痛感しました。